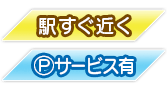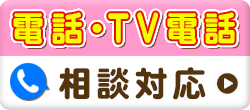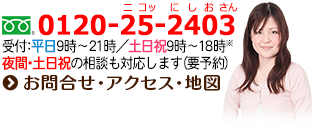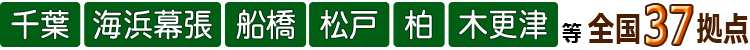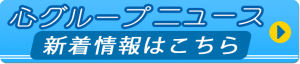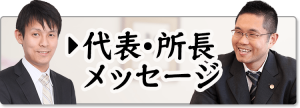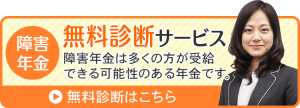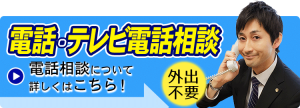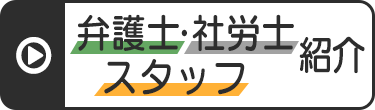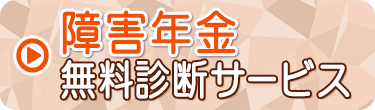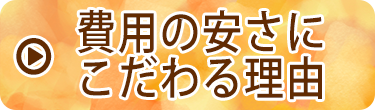筋ジストロフィーで障害年金を受け取れる場合
1 筋ジストロフィーの特徴
筋ジストロフィーとは骨格筋の壊死や再生を主病変とする遺伝性筋疾患を総称したもののことをいいます。
筋ジストロフィーは、筋肉を正しく作ったり、守ったりするタンパク質が、遺伝子の異常で作られなかったり、うまく機能しなかったりすることよって生じます。
その結果、筋萎縮や脂肪化、線維化が生じて筋力が低下し、運動機能障害を始めとした各種機能の障害を生じます。
以下では、主たる症状である運動機能障害を理由に障害年金を受給する場合について解説いたします。
2 筋ジストロフィーの障害認定基準
筋ジストロフィーを理由として運動機能障害が生じている場合、「肢体の機能の障害」として、障害認定がなされます。
障害認定の基準は以下のとおりです。
なお、肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定するとされており、関節可動域と筋力の計測を重視する「上肢の障害」及び「下肢の障害」とは異なり、日常生活における動作がどの程度不自由になっているかを重視しています。
⑴ 1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を独力で送ることが不可能な程度のもの
⑵ 2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3 筋ジストロフィーにより障害年金を受給できる具体例
「肢体の機能の障害」の認定基準は上記2のとおりですが、認定基準の内容をより細かく説明している認定要領では、等級に該当するものとして以下が例示されています。
⑴ 1級
・一上肢及び一下肢の機能障害により、日常生活における動作のすべてが一人で全くできない状態またはこれに近い状態となったもの
・四肢の機能障害により、日常生活における動作の多くが一人で全くできない状態または日常生活における動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な状態となったもの
⑵ 2級
・一上肢及び一下肢の機能障害により、日常生活における動作の多くが一人で全くできない状態または日常生活における動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な状態となったもの
・四肢の機能障害により、日常生活における動作の一部が一人で全くできない状態またはほとんどが一人でできてもやや不自由な状態となったもの
⑶ 3級
・一上肢及び一下肢の機能障害により、日常生活における動作の一部が一人で全くできない状態またはほとんどが一人でできてもやや不自由な状態となったもの