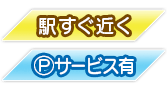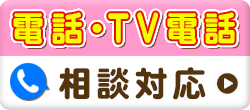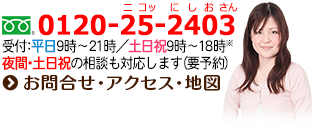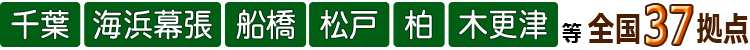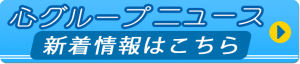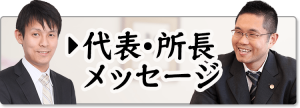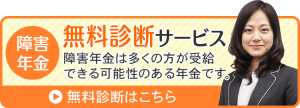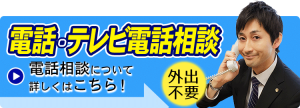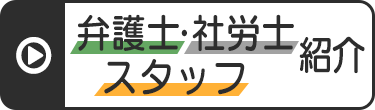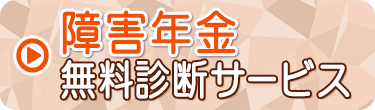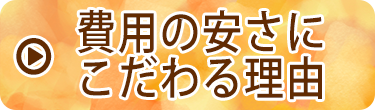狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
1 障害の分類について
障害年金の心疾患による障害の認定基準の中に認定要領があり、狭心症は虚血性心疾患の一つとして位置づけられています。
2 どのような症状があれば、狭心症で障害年金が認められる可能性があるか
虚血性心疾患の認定要領では、心不全あるいは狭心症等の症状の有無、異常検査所見の有無や数、日常生活や就労が受ける制限の程度を表す一般状態区分表の区分に応じて、等級を判断する仕組みとなっています。
異常検査所見は、9種類が認定要領に列挙されており、その内容は、安静時の心電図、負荷心電図、心エコー図、胸部Ⅹ線の検査結果に現れる一定の所見の有無、左室駆出率(EF)、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)の値、重症冠動脈狭窄病変の程度となっています。
また、一般状態区分表は、その障害によって日常生活や仕事がどのくらい制限を受けているのかを、最も軽い全く制限なし(ア)から最も重いほとんど寝たきりのような状況(オ)まで、5段階で評価するものです。
そのため、狭心症で障害年金を受給するには、きちんと病院に通院して、異常検査所見の有無について医師の検査を受けておくことと、日常生活や仕事の制限の程度を医師に誤解されないよう正確に伝えることの2つが、非常に重要なポイントとなります。
3 その他のポイント
また、狭心症以外の心疾患がある場合には、初診日の特定がポイントになる可能性があります。
一口に心疾患といっても、認定基準に分類されているように様々な疾患があります。
例えば、狭心症を発症して病院で診察を受ける5年程前に大動脈解離を経験されていた場合、5年前の大動脈解離による受診が初診日となるのか、直近の狭心症による受診が初診日となるのかが問題となることも考えられます。
この点は、医学的見地から、前発傷病が後発傷病との間に相当因果関係があるかという基準で判断されるため、事前に主治医の見解を確認しておく必要があると考えられます。